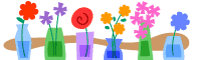 |
ここは憩いとくつろぎのコーナーです。 どうぞ、ごゆっくりお過ごしください。メニューも少しずつ、増やしていくつもりです。 |
| HOME|風の喫茶室|大橋五景|舞子歌枕|神戸国際行政書士事務所|日本語への旅| |
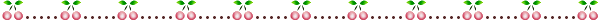 |
 メニュー1 時計のある風景 メニュー1 時計のある風景 |
|
だれにでも行きつけの喫茶店というものが一軒くらいはあるものだ。 ぼくの場合、M駅に近い「クロノス」という店がそれだった。 「クロノス」は表通りから少しはずれた古ぼけたビルの二階にある。あたりはちょっとした街の盲点のようになっていて、駅前のにぎわいがまるでうそのように、いつもひっそりとしている。 せまい階段を上がって店の中に入ると、まず澄みきったチェンバロの音色が耳にやさしい。板張りの床に使い込んだ樫の木の椅子とテーブル。さほど広くない店内だが、客の姿はいつもまばらだ。 その落ち着いた雰囲気がすっかり気に入って、いつの頃からか行きつけの店のひとつになってしまった。 偶然この店を見つけたときは、掘り出し物にぶつかった気分だった。 こういう店は人には教えない。自分だけのとっておきの場所、というわけだ。 人とのつきあいのわずらわしさに飽きたとき、あわただしい毎日の生活のテンポに疲れたとき、ぼくは「クロノス」に行く。 ひげのおじさんがポットのまま運んでくれるコーヒーは二杯分で五百円だ。 その二杯をたっぷり時間をかけて飲みながら、考えごとにふけったり、気に入った本を開いてみたり。 そうしていると、時のたつのも忘れ――いや、忘れようがないのだ。 それというのも、店の中はいたるところ時計だらけなのだ。 それも骨董屋のすみっこに転がっていたような古時計ばかり。 この時計のコレクションが「クロノス」のご自慢なのだ。 片隅の戸棚には時計についての古い書物も並べられている。 時計の森に迷いこむとかえって時間がわからない。 無数の時計の中にも、正しい時を刻んでいるのがいくつかあるはずだが、それがどれなのかわからない。 不思議な感覚なのだ。 街の人波から取り残されたこの喫茶店は、時の流れからも取り残されている。 ここは古い時計、過ぎ去った時間たちの安息の場…。 気のせいか、あたりの空気も古い写真のセピア色に染まっているようだ。 「クロノス」はひげのおじさんがひとりでやっている。 無口で、いつもカウンターの奥でむずかしい顔をしながらコーヒーカップをみがいている。 長年時計の間にうずもれて暮らしていたせいか、そのひげも八時二十分を指しているようだ。 何度も店に通っているうちに、ひとつの好奇心がしだいにふくれあがってきた。 一体、この店にはいくつの時計が飾ってあるのだろう? それに、これだけの時計をどうやって集めたのだろう? 一度、勘定のついでにおじさんにそのことを聞いてみた。 「立派なコレクションですね。これだけ集めるのはさぞ大変だったでしょう?」 「まあ……ね。」おじさんの返事はあいまいだった。 「一体いくつあるんですか?」 「さあ、一体いくつだろうね。お客さん、一度数えてごらんになったら?」 おつりを出しながら、おじさんはぼそぼそと言った。 その言葉がどこか挑戦するように聞こえたので、ぼくも意地になった。 その次からは、行くたびに時計の数を数えるようになった。 この壁にいくつ、あちらの棚にいくつ。 テーブルのかげや家具のすみにも見落としがないかどうか確かめた。 その日、客はぼく一人だった。 ぼくは少し意気ごんでいた。注文したコーヒーを飲むのもそこそこに、カウンターごしにおじさんに声をかけた。 「わかったよ、二〇七個だね、おじさん。」 「惜しい。残念だね。二〇八個だよ。」 おじさんはカウンターの向こうから顔を出してめずらしくにやっと笑った。 「えっ、そんなはずはない。ぼくはずいぶん確かめ……」 「いいかね、お客さん。わしの顔をじっと見るんだ。」 そう言っておじさんはぼくの顔をのぞきこんだ。 一体何が起こるのだろう?ぼくは胸がどきどきしてきた。 おじさんの顔が大きく目の前に迫ってきた。 チョビひげが八時二十分から動き出して、ぐるぐる回りはじめた。 おかしい、胸の動悸が少しずつ変わりはじめた。 ドキドキ……。 トキトキ……。 コチコチ……。 「さあ、上出来だ。鏡を見るかね。二〇八個目は振り子つきだよ。」 おじさんははじめて大きく笑った。 こうしてぼくは今、「クロノス」の戸棚の上で少しほこりをかぶりながら遅れがちに時を刻んでいる。 ドアが開いた。また一人、時計の森に迷いこんできた。 ぼくによく似た男だった。 |
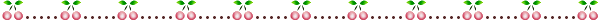 |
| HOME|風の喫茶室|大橋五景|舞子歌枕|神戸国際行政書士事務所|日本語への旅|自治文化通信 |
|
